
生ごみ処理機のランニングコストは、電気代や消耗品の交換費用などがかかります。購入を検討する際、どれくらいのコストがかかるのか、どのように節約できるのかを知ることは重要です。本記事では、処理方式ごとのランニングコストの違い、節約のポイント、助成金の活用方法について詳しく解説します。生ごみ処理機の導入を考えている方に役立つ情報を提供します。
この記事のポイント
- 生ごみ処理機のランニングコストの内訳が理解できる
- 処理方式ごとのコストの違いを知ることができる
- 電気代や消耗品の節約方法がわかる
- 助成金を活用して費用を抑える方法がわかる
もくじ
生ごみ処理機ランニングコストの基礎知識

- 生ごみ処理機とは?
- 生ごみ処理機の種類
- 生ごみ処理機のメリット・デメリット
生ごみ処理機とは?
生ごみ処理機は、家庭から出る生ごみの量と臭いを減らすことを目的とした家電製品です。使用することで、ごみ捨ての回数を減らし、コバエなどの害虫の発生を抑え、衛生的な環境を維持することができます。また、処理後の生ごみは堆肥として再利用できるため、資源の有効活用にもつながります。
生ごみ処理機の仕組みと目的
生ごみ処理機は、生ごみを乾燥させたり、微生物の力で分解したりすることで、ごみの減量化と臭いの抑制を実現します。これにより、ごみ出しの頻度が減るだけでなく、生ごみが原因となるコバエや悪臭の発生を抑えることができます。さらに、処理後の生ごみを堆肥として家庭菜園やガーデニングに活用できるため、環境にも優しい仕組みとなっています。
生ごみ処理機の種類
生ごみ処理機には、主に「乾燥式」「バイオ式」「ハイブリッド式」の3つの種類があります。
乾燥式
乾燥式は、高温の温風を利用して生ごみを乾燥させる方式です。水分を蒸発させることで、ごみの体積を減らし、臭いの発生を抑えます。コンパクトで屋内設置が可能な機種が多い点が特徴ですが、処理時の音が大きくなることがあります。また、ヒーターを使用するため、消費電力が高い傾向にあります。ルーフェン、パリパリキュー、パリパリキューライト、パナソニックなど

バイオ式
バイオ式は、微生物の働きを利用して生ごみを分解する方式です。バイオチップと呼ばれる微生物の基材と生ごみを混ぜることで、分解を促進します。一般的に屋外設置向けで、大型の機種が多いのが特徴です。脱臭機能がない場合、発酵臭が気になることがあるため、設置場所に注意が必要です。
バイオ式には手動タイプと自動タイプがあり、手動タイプは電気を使用しないため電気代がかかりません。一方で、自動タイプは脱臭機能などの電力を必要とするため、電気代がかかる場合があります。また、バイオ基材は定期的に交換する必要があります。バイオクリーン、自然にカエルなど

ハイブリッド式
ハイブリッド式は、乾燥式とバイオ式の両方の機能を兼ね備えた方式です。最初に温風で乾燥させた後、微生物で分解するため、臭いの発生が少なく、お手入れが比較的簡単です。消費電力は乾燥式よりも低い傾向があり、電気代と消耗品のコストのバランスが良いとされています。
ただし、大型の機種が多く、設置スペースを確保する必要があります。また、バイオ基材の定期的な交換が必要です。ナクスルなど

生ごみ処理機のメリット・デメリット
生ごみ処理機は、家庭での生ごみ処理を効率化し、環境負荷を低減するための有効な手段となります。しかし、導入にあたってはメリットとデメリットを十分に理解しておくことが重要です。
生ごみ処理機のメリット
生ごみ処理機を導入することで、多くの利点が得られます。
生ごみの減量が可能になり、水分を除去することで体積が大幅に減少します。これにより、ごみ出しの頻度が減り、指定ごみ袋の使用量を削減できます。例えば、乾燥式処理機では処理後のごみが約20分の1に減量できる機種もあります。
また、悪臭の軽減にも貢献します。生ごみ処理機は密閉された状態で生ごみを処理するため、腐敗による臭いの発生を抑制します。特に夏場のように生ごみが腐敗しやすい時期には、効果的な悪臭対策となります。
さらに、衛生面の改善にもつながります。生ごみを放置すると害虫が発生しやすくなりますが、生ごみ処理機を使用することで虫の発生を抑え、キッチンを清潔に保つことができます。
環境への貢献も重要なポイントです。生ごみを燃えやすい状態にすることで焼却時の省エネにつながり、ごみ処理場の負担を軽減します。また、二酸化炭素の排出量削減にも貢献します。
最後に、処理後の生ごみは堆肥として再利用できます。家庭菜園やガーデニングを行っている場合、有機肥料として活用できるため、肥料代の節約にもなります。ただし、生ごみ処理機で作られた堆肥の肥料としての効果や安全性については、各製品の取扱説明書をよく確認する必要があります。
生ごみ処理機のデメリット
一方で、生ごみ処理機の導入にはいくつかのデメリットも存在します。
まず、電気代の負担が挙げられます。特に乾燥式の機種は電気代が高くなる傾向があり、消費電力や処理時間によっては月額1,000円を超える場合もあります。ただし、省エネ設計の機種を選ぶことで、電気代を抑えることが可能です。
また、メンテナンスの手間も考慮する必要があります。生ごみ処理機を効果的に運用するためには、定期的な容器の清掃や脱臭フィルター、バイオチップなどの消耗品の交換が必要です。これらの作業を面倒に感じる人もいるかもしれません。
運転音の問題もあります。特に乾燥式の機種は運転中に騒音が発生することがあり、夜間の使用を避けたり、静音性に優れた機種を選ぶなどの対策が求められます。
さらに、処理能力には制限があります。家庭用生ごみ処理機では、一度に処理できる量が限られているため、大家族や調理頻度の高い家庭では処理能力が不足する可能性があります。
最後に、設置場所の確保が必要です。生ごみ処理機はある程度のスペースを必要とするため、キッチンが狭い場合や収納スペースが限られている場合には設置が難しいことがあります。特に屋外専用の機種では、雨風が当たらない場所を確保する必要があります。
これらのメリット・デメリットを理解した上で、自宅に適した生ごみ処理機を選ぶことが重要です。
生ごみ処理機ランニングコストの詳細
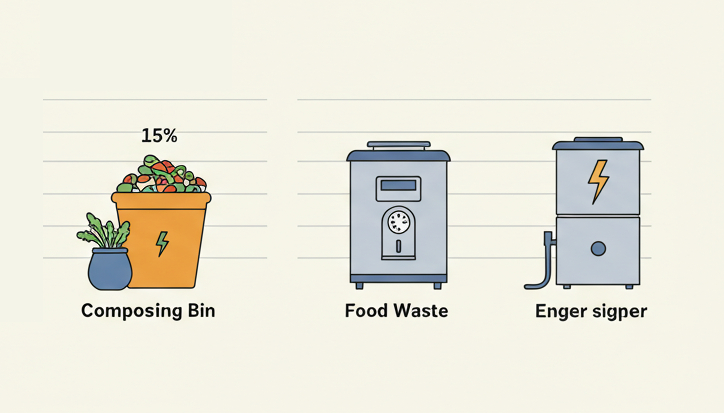
- 電気代
- 電気代の節約方法
- 消耗品
- メンテナンス
- 処理方式別のランニングコスト比較
- ランニングコストを抑えるための選び方
- 人気機種のランニングコスト事例
- 自治体の助成金制度
生ごみ処理機を維持するためには、電気代や消耗品の交換費用など、さまざまなランニングコストが発生します。これらのコストを把握し、節約することで、より経済的に生ごみ処理機を利用することができます。
電気代
生ごみ処理機のランニングコストの中でも、電気代は大きな割合を占めます。電気代は、処理方式や機種、使用頻度によって異なります。
乾燥式は、ヒーターを使用して温風で生ごみを乾燥させるため、消費電力が高く、電気代も比較的高くなります。例えば、パナソニックの「MS-N53XD」の場合、標準モードで1回あたり約30円、ソフト乾燥モードで約37円の電気代がかかります。ただし、処理時間は生ごみの種類や量、水切りの状態によって変動します。
バイオ式は、微生物の働きで生ごみを分解するため、消費電力が比較的低くなります。手動式のバイオ式であれば電気代はかかりませんが、自動のバイオ式では脱臭機能などのために電気代が発生します。例えば、シャープの「NP-40CX」(生産中止)の場合、脱臭機能オフで1日あたり約12.3円、脱臭機能オンで約129円の電気代がかかっていました。
ハイブリッド式は、乾燥機能とバイオ分解機能を組み合わせているため、電気代は乾燥式より低い傾向があります。例えば、DENZENの「ナクスル」の場合、1時間あたり約1.62円、1日24時間使用すると約38.88円の電気代がかかります。
これらのコストを考慮しながら、使用頻度や機種の選択を行うことで、電気代の節約が可能になります。
生ごみ処理機の電気代比較(処理方式ごと)
生ごみ処理機の電気代を処理方式ごとに比較すると、以下のようになります。
| メーカー/商品名 | 処理方式 | 処理時間 | 電気代の目安 |
|---|---|---|---|
| パナソニック/MS-N53XD | 乾燥式(熱処理式) | 1〜9時間 | 標準モード:約20〜81円/日 ソフト乾燥モード :約23〜91円/日 |
| ルーフェン | 乾燥式(温風循環式) | 1〜8時間 | 約20〜40円/回 |
| パリパリキューPPC-11 | 乾燥式 | 1〜24時間 | パリパリモード: 約28〜45円/日、 ソフトモード: 約16〜23円/日 |
| 自然にカエル | バイオ式(手動) | 24時間 | 0円/日 |
| バイオクリーン | バイオ式 | 24時間 | 約81.6円/日 |
| ナクスル | ハイブリッド式 | 24時間 | 約20円/日 |
※これらの数値はあくまで目安であり、使用環境や容量、設定によって異なることに注意が必要です。
電気代の節約方法
生ごみ処理機の電気代を抑えるためには、いくつかの工夫が有効です。
生ごみの量を減らして乾燥時間を短縮
生ごみの水気をしっかり切ることで、処理にかかる時間と電気代を削減できます。また、食材は必要な分だけ購入し、使い切ることで生ごみの発生自体を減らすことも節約につながります。
生ごみをまとめて処理する
特に熱処理式の場合、できるだけ生ごみをまとめて処理することで、処理機の使用回数を減らし、電気代の節約が可能です。ただし、バイオ式やハイブリッド式は生ごみが出るたびに投入して処理する仕組みのため、まとめて処理する必要はありません。
長期間使用しないときの対応
長期間使用しない場合は、電源を切ることが推奨されます。特に熱処理式では、1週間以上使用しない場合には、コンセントから電源プラグを抜いて待機電力を抑えるとよいでしょう。ただし、バイオ式やハイブリッド式では、数日程度の不使用であれば電源をつけたままにしておいた方が適切な場合もあります。製品の取扱説明書を確認し、適切な電源管理を行うことが重要です。
省エネ設計の生ごみ処理機を選ぶ
省エネ設計の生ごみ処理機を選ぶことも電気代の節約につながります。省エネ設計の機種では、処理中の温度や湿度の管理、撹拌の工程などが自動で調整され、処理が終了すると自動で電源が切れるか、節電モードに移行する機能が備わっています。このような機能を活用することで、効率的に電気代を抑えることができます。
消耗品
生ごみ処理機を維持するためには、脱臭フィルターの交換、バイオチップ(バイオ式の場合)、乾燥促進剤、バスケットカバーなどの消耗品が必要になります。これらの消耗品について説明します。
脱臭フィルターの交換
生ごみ処理機の脱臭フィルターは、生ごみの臭いを吸収し、快適な使用環境を保つために重要です。脱臭フィルターの交換頻度は、使用頻度や処理内容によって異なります。
パリパリキューブシリーズでは、モデルによって交換目安が異なります。パリパリキューライト(PCL-35)は4ヶ月から6ヶ月、パリパリキュー(PPC-11)は4ヶ月から9ヶ月が交換目安です。交換用脱臭フィルターは、販売店またはオンラインストア(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)で購入できます。
「パリパリキュー」シリーズの脱臭フィルターは、販売店や時期によって価格が異なりますが、一般的には2個入りで約5,000円から6,000円程度で販売されています。例えば、Amazonでは5,144円、Yahoo!ショッピングでは6,270円で販売されています。

ルーフェンの活性炭フィルターは、定期コースで3ヶ月に1回の交換が推奨され、単品購入も可能です。価格は、バスケットカバー(20枚入)が単品2,280円(税抜)、定期コースでは毎月1,980円(税抜)です。活性炭フィルター(2本入り)は単品2,980円(税抜)、定期コースではバスケットカバーとセットで4,280円(税抜)/月で提供されています。バスケットカバーは必須ではありません。

バイオチップ(バイオ式の場合)
バイオ式生ごみ処理機では、微生物が生ごみを分解するためにバイオチップが必要です。バイオチップは、微生物を育成するための基材であり、定期的に交換する必要があります。
乾燥促進剤
乾燥式生ごみ処理機では、乾燥効率を高めるために乾燥促進剤を使用する場合があります。
メンテナンス
生ごみ処理機を効果的に運用するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。ここでは、清掃の手間と方法、故障時の修理費用について解説します。
清掃の手間と方法
生ごみ処理機の種類によって清掃方法は異なります。パリパリキューブでは、本体上部を乾燥処理後に水で濡らしたやわらかい布で軽く水拭きし、汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を薄めて拭き取ります。処理容器やバスケット、押えカバーは運転終了後に水洗いでき、素材はプラスチック製のため、台所用中性洗剤で洗うことも可能です。汚れがひどい時はぬるま湯で浸け置きするのも有効ですが、食器乾燥機や食器洗浄機の使用は避ける必要があります。
ルーフェンの場合、バスケットの汚れが気になったら水洗いが可能で、食洗機の使用もできます。また、フィルターケースに水が溜まると臭いの原因になるため、定期的な水洗いが推奨されます。本体は水洗い不可のため、注意が必要です。
パナソニックの家庭用生ごみ処理機「MS-N53XD」は、水洗いでのお手入れが可能な設計になっています。
手入れの頻度が少なく、方法が簡単な機種を選ぶと、維持管理が楽になります。生ごみを入れる容器やその他付属品が取り外し可能な機種は、清掃がしやすく便利です。
故障時の修理費用
多くの生ごみ処理機では、1年間の保証期間が設けられており、取扱説明書に従った使用状態での不良に対して、交換または修理対応を受けることができます。ただし、お客様の故意・過失による故障は保証の対象外となります。また、初期不良以外での返品は受け付けていません。
処理方式別のランニングコスト比較
生ごみ処理機のランニングコストは、処理方式によって異なります。
乾燥式:電気代が高い傾向
乾燥式は、ヒーターを使用して温風で乾燥させるため、消費電力が高く、電気代が高くなる傾向があります。月の電気代が1,000円を超えるケースも珍しくありません。例えば、パナソニックの熱処理式生ごみ処理機「MS-N53XD」の場合、電気代は標準モード(約2時間15分)で1回あたり約30円、ソフト乾燥モード(約3時間30分)で約37円となっています。
バイオ式:電気代は低いが、バイオ基材の交換が必要
バイオ式は、微生物の働きで生ごみを分解するため、手動タイプであれば電気代はかかりません。しかし、自動タイプでは脱臭機能の有無によって電気代が異なります。例えば、シャープのバイオ式生ごみ処理機では、脱臭機能をオフにした場合1日あたり約12.3円、オンの場合は約129円の電気代がかかります。また、バイオ基材を定期的に交換する必要があり、それによるランニングコストも発生します。
ハイブリッド式:電気代と消耗品コストのバランス
ハイブリッド式は、乾燥式とバイオ式のメリットを組み合わせた方式で、電気代は比較的安い傾向にあります。例えば、DENZENのハイブリッド式生ごみ処理機「ナクスル」の場合、電気代は1時間あたり約1.62円、1日24時間使用すると約38.88円かかります。また、バイオ式と同様にバイオチップの定期的な交換が必要となります。
生ごみ処理機のタイプごとのランニングコストの目安は、乾燥式とバイオ式で500~1,500円/月、ハイブリッド式では1,500円~2,000円/月となります。電気代は消費電力だけでなく、稼働時間の長さによっても変動するため、使用頻度やライフスタイルに合わせた機種選びが重要です。
ランニングコストを抑えるための選び方
生ごみ処理機のランニングコストを抑えるためには、機種選びが重要です。
省エネ設計の機種を選ぶ
省エネ設計の生ごみ処理機を選ぶことで、電気代を節約できます。温度や湿度の管理、撹拌の工程などを自動で調整し、処理が終了すると電源が自動で切れる、または節電モードに移行する機種は、消費電力を抑えるのに効果的です。
処理容量を考慮する
処理容量は、生ごみ処理機が一度に処理できる生ごみの量を示します。家族の人数や料理の頻度を考慮して、適切な容量の機種を選ぶことが重要です。家庭ごみの約3割は生ごみとされており、環境省の調査では1人あたり1日約890グラムのごみを排出しているとされています。これを基に計算すると、1人あたりの生ごみの排出量は約260グラムになります。家族全員の排出量を考慮し、適切な容量の機種を選ぶことで、効率的に処理ができ、余分な電気代を抑えられます。
メンテナンスが容易な機種を選ぶ
頻繁に使用する生ごみ処理機だからこそ、メンテナンスが簡単な機種を選ぶことも重要です。例えば、容器内に水を注ぐだけで掃除ができる「クリーンモード」搭載の機種や、生ごみを入れる容器や付属品を簡単に取り外して洗浄できるモデルは、お手入れがしやすくなります。ルーフェンのバスケットは食洗機での洗浄も可能で、手間を省くのに役立ちます。
人気機種のランニングコスト事例
人気の生ごみ処理機のランニングコストについて解説します。
島産業 パリパリキューブシリーズ

島産業のパリパリキューブシリーズは、乾燥式の生ごみ処理機で、水切りだけで簡単にセットできる手軽さが魅力です。特に「PPC-11」は使い勝手が良く、幅広いユーザーにおすすめのモデルです。
電気代は、パリパリモードで約28円~45円、ソフトモードで約16円~23円となっています。また、下位モデルである「パリパリキューライト」は、節電モードで約13円~17円、通常モードで約27円と、さらに省エネ性能に優れています。
脱臭フィルターの交換目安は、使用頻度によりますが、通常1個あたり4~9ヶ月が目安です。例えば、「パリパリキューライト(PCL-35)」は4~6ヶ月、「パリパリキューブライトアルファ(PCL-51)」は4~9ヶ月、「パリパリキューブ(PPC-01)」は4~6ヶ月での交換が推奨されています。
また、バスケット用水切りネットの使用が推奨されており、不織布タイプよりも網状のネットを使用すると乾燥効率が向上します。付属の水切りネットのサイズは横28cm×縦25cmで、素材にはポリエチレン(PE)が使用されています。
パナソニック 家庭用生ごみ処理機 MS-N53XD

パナソニックのMS-N53XDは、1回あたりの処理容量が多く、処理時間が短いのが特徴です。電気代は、標準モード(約2時間15分)で1回あたり約30円、ソフト乾燥モード(約3時間30分)で約37円となっています。処理時間は、標準モードで約1時間40分~5時間40分、ソフト乾燥モードでは約2時間10分~8時間30分の範囲で変動します。
また、脱臭機能にはプラチナパラジウム触媒を採用しているため、フィルターを使わずに臭いを抑える工夫がされています。
ルーフェン

ルーフェンは温風循環式の生ごみ処理機で、電気代は約20〜40円と比較的低めです。活性炭フィルターは3ヶ月に1回の交換が必要で、臭い対策のために定期的なメンテナンスが求められます。また、バスケットカバー(20枚入)を毎月交換することで、日々の手入れやゴミ捨てが簡単になり、衛生的に使用できるのが特徴です。
自治体の助成金制度
生ごみ処理機の購入に際して、自治体によっては助成金が支給される場合があります。助成金を利用することで、初期費用の負担を軽減できるため、購入を検討する際にはぜひ活用したい制度です。
助成金制度の確認方法
助成金制度の有無や詳細を確認するには、お住まいの地域の市区町村役場に問い合わせるのが最も確実です。また、多くの自治体では公式ウェブサイトで情報を公開しているため、「〇〇市 生ごみ処理機 助成金」などのキーワードで検索することで、最新の情報を得ることができます。
申請のタイミングと注意点
助成金の申請タイミングは自治体によって異なり、購入前に申請が必要な場合と、購入後に申請できる場合があります。購入前に申請が必要な場合は、助成金の交付決定を受けた後でないと購入できないため、事前に確認が必要です。一方、購入後に申請できる場合は、生ごみ処理機の領収書など必要書類を揃えて手続きを行うことになります。
申請の際には、必要事項の記入や領収書の提出が求められるため、各自治体の規定を確認し、漏れのないように準備しましょう。
生ごみ処理機ランニングコストの内訳理解:まとめ
- 生ごみ処理機のランニングコストには電気代・消耗品費・メンテナンス費が含まれる
- 乾燥式は電気代が高め、バイオ式は消耗品費がかかる
- ハイブリッド式はバランスが取れたコスト設計になっている
- 電気代を抑えるために省エネ設計の機種を選ぶとよい
- 処理容量を考慮し、家庭に合った機種を選ぶことが大切
- 定期的なメンテナンスを行うことでコストを最適化できる
- バイオチップや脱臭フィルターの交換時期を把握することが重要
- 自治体の助成金制度を利用すると初期費用を抑えられる
- ランニングコストは月額500円~2,000円程度が目安
- 節電モードやクリーンモード搭載機種はランニングコスト削減に役立つ
- 使用頻度によってランニングコストが大きく変わる
- メンテナンスが容易な機種を選ぶことで手間を減らせる
- 初期投資だけでなく、長期的なコストを考慮して機種を選ぶ
- 助成金の有無は自治体のホームページで確認できる
- 生ごみ処理機を選ぶ際にはコストパフォーマンスも重要なポイント